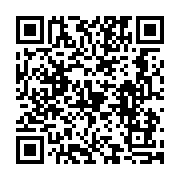自己肯定感を高めて人生を前向きに!
初めての方はこちらのオススメ記事をお読みください一覧はこちら
重大な加害を『いじめ』にすり替えるな|言葉と責任の問題
暴行や性加害の深刻な被害が
「いじめ」という言葉に置き換えられるとき、
その本質は見えなくなります。
そして
その曖昧さの裏で、
大人や社会は責任を回避し、
被害者は一生消えない傷を背負わされます。
【vol.2207】
こんにちは!
カウンセリングオフィス
プログレスのむかいゆかです。
今日から
夏の甲子園が開幕しましたね。
個人的には、何年も前から
「この暑い中、命懸けでようやるわ…」と
冷ややかにその行方を見ていますが
今年も、直前になって、
こんなニュースが飛び交い
私の視線は更に冷ややかになってます。
「いじめ」という言葉で矮小化される
深刻な被害
これ、立派な暴行で犯罪です。
けれど、未成年の子どもがすると
暴行が「いじめ」と表現されて
その深刻度が矮小化されてしまいがちです。
先月末にも、三重県の女子高校生が
交際相手の男子生徒から
繰り返し性的暴行を受けていた事件が
明るみに出ましたが
学校側の認識はあくまでも
「いじめの重大事態」。
いやいや
学校の屋外や校内などで
20回以上も受けていた性被害を
「いじめ」で片付けるだなんて
あまりにも酷い話です。
言葉の置き換えが生む
構造的な責任回避
こうして何でも
「いじめ」という言葉で
まとめてしまうことで
事態の深刻さは見えなくなります。
本来「暴行」や「性犯罪」と
正しく名前をつければ
それは刑事事件として扱われるべきもの。
しかし「いじめ」という
ラベルが貼られた瞬間、
それは“学校内の問題”に変換され
対応の枠組みも優先度も
大きく変わってしまいます。
しかも
「将来があるのだから…」という理由で
加害者やその周囲に過剰に配慮する大人たち。
その結果、被害者は何も悪くないのに、
あまりにも重い荷物を
一生背負わされることになります。
私は、こうした言葉の置き換えは
大人が引け腰になって
責任を引き受けていない表れだと思います。
学校も、高野連も、時には社会全体までもが
本来向き合うべき事実から目をそらし、
“無難な言葉”に包んでやり過ごしてしまう。
でも、そのツケを払うのは
いつも弱い立場にある者です。
そして、こういった「なあなあ」の文化は
同じことが繰り返される温床にもなります。
言葉は、ただの記号ではありません。
ラベルひとつで
人の人生の重みや方向が
大きく変わってしまう力が
そこには潜んでいます。
だからこそ
事実を事実として呼ぶ勇気を
私たちは持たなければなりません。
では、私たち大人は
どう関わればいいのか。
それは決して
難しいことではありません。
暴力や性加害を見聞きしたとき
まず「これは犯罪だ」と
正しく認識すること。
そして、その事実を曖昧にせずに
適切な機関や制度につなげていくこと。
「いじめ」という
便利な棚に押し込むのではなく
法的にも社会的にも適切な名前をつけること。
その一歩が、次の被害を生まないための
何より確かな予防策になるはずです。
“大好きな”夏の甲子園が
始まったばかりですが
まずは熱戦よりも
この問題について吠えておきました。

お問い合わせ

| 住所 | 〒060-0042 札幌市中央区大通西1丁目14-2 桂和大通ビル50 9F マップを見る |
|---|---|
| 営業時間 | 【火~金】13:00~20:15 【土】10:00~17:00 |
| 定休日 | 日・祝日・月 |
関連記事
カテゴリー
- AEDP®︎心理療法 (38)
- HPメイン (2)
- おすすめ (31)
- からだとこころ (90)
- ご挨拶/お知らせ (28)
- わたしが大切にしてること (191)
- カップルセラピー/カウンセリング (17)
- ストレスマネジメント (122)
- セラピー/カウンセリング一般 (239)
- トラウマ/心の傷 (86)
- 人間関係 (64)
- 夫婦/恋愛 (22)
- 女性としての生きづらさ (31)
- 専門家向け (20)
- 性格 (4)
- 愛着/アタッチメント (13)
- 感情を扱う (149)
- 研修/トレーニング (34)
- 経営者向け (14)
- 自分らしく生きる (193)
- 自己肯定感 (119)
- 親子 (37)
人気記事(トータル)
人気記事(月間)
月別
- 2026年2月 (28)
- 2026年1月 (31)
- 2025年12月 (31)
- 2025年11月 (30)
- 2025年10月 (31)
- 2025年9月 (30)
- 2025年8月 (31)
- 2025年7月 (31)
- 2025年6月 (30)
- 2025年5月 (31)
- 2025年4月 (30)
- 2025年3月 (31)
- 2025年2月 (28)
- 2025年1月 (31)
- 2024年12月 (32)
- 2024年11月 (31)
- 2024年10月 (31)
- 2024年9月 (31)
- 2024年8月 (32)
- 2024年7月 (31)
- 2024年6月 (31)
- 2024年5月 (31)
- 2024年4月 (30)
- 2024年3月 (31)
- 2024年2月 (30)
- 2024年1月 (31)
- 2023年12月 (31)
- 2023年11月 (31)
- 2023年10月 (32)
- 2023年9月 (30)
- 2023年8月 (33)
- 2023年7月 (32)
- 2023年6月 (31)
- 2023年5月 (31)
- 2023年4月 (31)
- 2023年3月 (32)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (32)
- 2022年12月 (31)
- 2022年11月 (30)
- 2022年10月 (31)
- 2022年9月 (30)
- 2022年8月 (31)
- 2022年7月 (31)
- 2022年6月 (30)
- 2022年5月 (31)
- 2022年4月 (29)